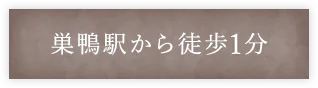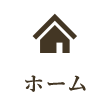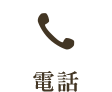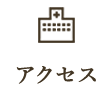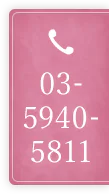潰瘍性大腸炎について
 潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に「びらん」と呼ばれる浅いただれや潰瘍が形成される、原因不明の慢性炎症性疾患です。病態生理として、本来であれば自己以外のものから身体を守るはずの免疫機構に異常が発生し、自己の大腸を攻撃して炎症を誘発することが知られています。通常、炎症は直腸から始まり、腸管粘膜の全周にわたって連続的に広がります。また、治療によって症状が改善される寛解と再び悪化する再燃とを繰り返す「再燃寛解型」の経過をたどる症例が多いのも、この疾患の特徴です。
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に「びらん」と呼ばれる浅いただれや潰瘍が形成される、原因不明の慢性炎症性疾患です。病態生理として、本来であれば自己以外のものから身体を守るはずの免疫機構に異常が発生し、自己の大腸を攻撃して炎症を誘発することが知られています。通常、炎症は直腸から始まり、腸管粘膜の全周にわたって連続的に広がります。また、治療によって症状が改善される寛解と再び悪化する再燃とを繰り返す「再燃寛解型」の経過をたどる症例が多いのも、この疾患の特徴です。
完治に至る治療法が確立されていないことから、潰瘍性大腸炎は、厚生労働省が定める指定難病の1つです。昭和45~55年頃までの日本では発症も稀でしたが、平成28年度の統計では患者数が約22万人にのぼり、依然として増加傾向が認められます。発症者は若年層に多く、男女とも20代が最多ですが、10代でも発症し、近年では中高年にも見られるようになっています。
原因
これまでのところ、発症機序の解明には至っていません。学術領域では、遺伝、感染症、食生活の欧米化、自己免疫機能の異常、腸内細菌の関与など、多岐にわたる角度から研究がなされていますが、原因も特定しきれていないのが現状です。もっとも、単一の要因が引き金になるわけではなく、複数の要因が密接に関連して発症するのではないかと考えられています。
また、同じ潰瘍性大腸炎であっても、軽症者から重症者まで、個々の症候の重篤度と経過、予後は人それぞれで、安定した状態を維持できる人もいれば寛解と増悪とを繰り返す人もいて、病態は様々です。
症状
- 貧血
- 発熱
- 腹痛
- 下痢
- 粘血便
- 皮疹や関節炎
など
検査・診断
 症状から潰瘍性大腸炎の徴候が示唆されたら、他の疾患と鑑別するために、大腸カメラ検査、血液検査、便培養検査を実施し、炎症が生じた粘膜の一部を大腸カメラ検査の際に数ヶ所で採取する病理診断も実施します。このとき、症状が類似した感染性腸炎を除外するために、感染症とも鑑別すべき点が重要です。
症状から潰瘍性大腸炎の徴候が示唆されたら、他の疾患と鑑別するために、大腸カメラ検査、血液検査、便培養検査を実施し、炎症が生じた粘膜の一部を大腸カメラ検査の際に数ヶ所で採取する病理診断も実施します。このとき、症状が類似した感染性腸炎を除外するために、感染症とも鑑別すべき点が重要です。
治療方針を決定する際には、病変の範囲を基準に、左側結腸炎型、全大腸炎型、直腸炎型に分類します。また、内視鏡検査の所見から重症度を軽症から重症まで評価し、血液検査の結果や自覚症状の度合いからも、軽症、中等症、重症の3段階で評価します。
さらに、クローン病とは異なり、潰瘍性大腸炎では、炎症時に増加するC炎症性タンパク質(CRP)に対する血液検査の数値が病態と相関せず、症状が悪化してもCRPが連動して上昇するわけではない点にも注意が必要です。
治療
 治療の軸にあるのは、免疫機構の働き過ぎを抑制する考え方です。このため、免疫抑制療法を中心にして治療計画を構築します。具体的には、寛解期に落ち着いた状態を維持して再燃を防ぐ「寛解維持療法」と、増悪時に症状を改善する「寛解導入療法」の2種類の治療法の組み合わせです。
治療の軸にあるのは、免疫機構の働き過ぎを抑制する考え方です。このため、免疫抑制療法を中心にして治療計画を構築します。具体的には、寛解期に落ち着いた状態を維持して再燃を防ぐ「寛解維持療法」と、増悪時に症状を改善する「寛解導入療法」の2種類の治療法の組み合わせです。
当院で治療が可能なのは、通院による外来診療で対応できる範囲の症状までにとどまります。このため、外来での対応が困難である(概ね中等症の後半から重症にあたる)患者様には、当院と連携して入院治療が可能な専門の医療機関を紹介いたします。入院治療で改善が得られたら、以後の寛解維持療法については当院での継続が可能です。
これに対して寛解導入療法では、軽症から重症まで、「5-ASA(ごあさ)製剤」と呼ばれる5-アミノサリチル酸製剤の投与を基本に組み立てます。5-ASAには、経口投与薬や直腸内投与薬など異なる剤形が存在し、投与設計にもいくつかのパターンが考えられます。直腸炎が軽症であれば、坐剤の5-ASAだけで治療することも可能です。
必要に応じた併用療法として、5-ASAの坐剤または注腸製剤を局所投与します。軽症や中等症の一部の症例では、5-ASA製剤による治療だけでも寛解が認められます。他に、泡状のステロイド注腸フォーム製剤、ステロイドの坐剤や注腸液剤も、局所投与の対象になる製剤です。
なお、内科的治療の範囲では症状を制御できず、増悪が認められる場合、大腸全摘出を原則とする外科手術によって治療を試みます。術後に人工肛門を選択するか、大腸のうち直腸の一部をわずかに残存させて肛門機能を維持するかは、手術の方式次第です。
潰瘍性大腸炎には完治に導く治療法が見つかってはいませんが、適切な治療を継続して寛解状態を維持することで、普段と変わらない生活を送ることができます。しかし、治療を途中でやめてしまうと悪化する場合があり、炎症が長引くと大腸がんの原因にもなり得るため、辛抱強く治療を続ける必要があります。
クローン病について
 クローン病は、潰瘍性大腸炎と同様に難病として指定されており、粘膜がただれた「びらん」や潰瘍が形成される炎症性疾患です。似たような疾患に潰瘍性大腸炎がありますが、潰瘍性大腸炎では炎症が大腸だけに限局されるのに対し、クローン病は口腔から肛門までの消化管のいかなる部位にも発生し得る点が異なります。また、クローン病の治療では食事の管理が重要な点も、潰瘍性大腸炎との違いです。発症機序は完全には明らかになっていませんが、免疫系に機能障害が発生して過剰に反応し、自己の消化管を攻撃すると考えられています。厚生労働省によれば、日本では約40,000人に見られ、現在も増え続けています。
クローン病は、潰瘍性大腸炎と同様に難病として指定されており、粘膜がただれた「びらん」や潰瘍が形成される炎症性疾患です。似たような疾患に潰瘍性大腸炎がありますが、潰瘍性大腸炎では炎症が大腸だけに限局されるのに対し、クローン病は口腔から肛門までの消化管のいかなる部位にも発生し得る点が異なります。また、クローン病の治療では食事の管理が重要な点も、潰瘍性大腸炎との違いです。発症機序は完全には明らかになっていませんが、免疫系に機能障害が発生して過剰に反応し、自己の消化管を攻撃すると考えられています。厚生労働省によれば、日本では約40,000人に見られ、現在も増え続けています。
原因
これまでのところ原因は不明ですが、免疫機構が不適切に活性化して自己の消化管を傷つけてしまうと考えられています。
症状
最も典型的な症状は、体重の著しい減少です。他に、腹痛や下痢、肛門の腫れや痛みが生じる場合もあり、痔になると通常よりも悪化しやすく治りにくい特徴があります。
体重減少
- 下痢
- 腹痛
- 肛門からの白い膿の排出、肛門の腫れや痛み
- 貧血
- 発熱
- 口内炎
- 消化管穿孔
- 腸閉塞・消化管狭窄
- 腹腔内膿瘍
- 関節痛
- 皮疹
など
検査・診断
 症状からクローン病の徴候が示唆されたら、大腸カメラ検査、腹部レントゲン検査、便培養検査、血液検査を実施します。ただし、肛門周囲膿瘍や複雑痔ろうで肛門に痛みがあって大腸カメラ検査の負担が大きい場合は、当院と連携した肛門外科で肛門の疾患を治療してから大腸カメラ検査を行う場合もあります。
症状からクローン病の徴候が示唆されたら、大腸カメラ検査、腹部レントゲン検査、便培養検査、血液検査を実施します。ただし、肛門周囲膿瘍や複雑痔ろうで肛門に痛みがあって大腸カメラ検査の負担が大きい場合は、当院と連携した肛門外科で肛門の疾患を治療してから大腸カメラ検査を行う場合もあります。
クローン病では、特に小腸から大腸への移行部である回盲部を中心に、大腸カメラ検査でクローン病特有の敷石像や縦走潰瘍が認められれば、概ね診断がつきます。あるいは、大腸カメラ検査と同時に粘膜の一部を採取して病理検査を実施し、診断の一助とする場合もあります。しかし、クローン病のなかには、大腸には異常がなく小腸や上部消化管だけに病変が発生するものもあります。
治療
クローン病では治療による完治を期待できないため、治療の第1目標として、主に薬物療法と食事療法で症状を安定させて制御し、ひいては生活の質(QOL)を維持することが挙げられます。クローン病にかかると、一生のうちで少なくとも1回は腹部の手術が必要になることが多く、症状の経過次第では何度も手術が必要になる場合もあります。もちろん、手術が最適な選択肢であればよいのですが、第2の目標として、可能な限り手術をしなくて済むように内科的な治療で症状を抑えることも重要です。
食事療法
食事療法では、基本的に、低脂肪の食事内容を組み立てます。これは、脂肪が消化管での過剰な免疫応答を誘発することが知られているためです。具体的には、炎症を悪化させる肉の脂身、バター、ラードなどの飽和脂肪酸、大豆油、コーン油、ごま油、マーガリンなどのn-6系脂肪酸をできるだけ避け、炎症を抑えるDHAやEPAを多く含む魚、菜種油やえごま油などのn-3系脂肪酸を積極的に摂取します。また、総合栄養剤であるエレンタールを服用すると、症状が改善されて栄養を補うこともできます。特に小腸に狭窄が生じている場合は腸閉塞を起こしやすいため、キノコ類、こんにゃく、繊維質の多い野菜や根菜類などの消化に悪い食材を食べないようにすることが大切です。
薬物療法
薬物療法では、基本薬として5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA製剤)を使用し、必要に応じて注射薬である生物学的製剤や免疫調節薬を併用しながら症状を制御します。症状が強い場合は、急性期のみ副腎皮質ステロイドで寛解導入療法を取り入れることも可能です。ステロイドの長期使用には効果がないだけでなく、副作用の恐れもあるため、投与後も少しずつ減量して最終的にはステロイドの投与を中止します。
肛門に病変がある場合、薬物療法だけで改善が期待できる場合もありますが、原則として肛門外科で治療を管理します。具体的には、複雑痔ろうの場合はシートン法による手術法を採用し、肛門周囲膿瘍では膿瘍を切除します。
クローン病は、時々、腹部膨満や突然の激しい腹痛、嘔吐が現れたり(腸閉塞)、発熱と突然の激しい腹痛を伴う腹腔内膿瘍や消化管穿孔が出現したりする、特有の合併症が見られる点にも注意が必要です。このような症状が出た場合は速やかに救急車を呼び、適切な医療機関を受診してください。多くの場合に、緊急外科手術が必要になります。